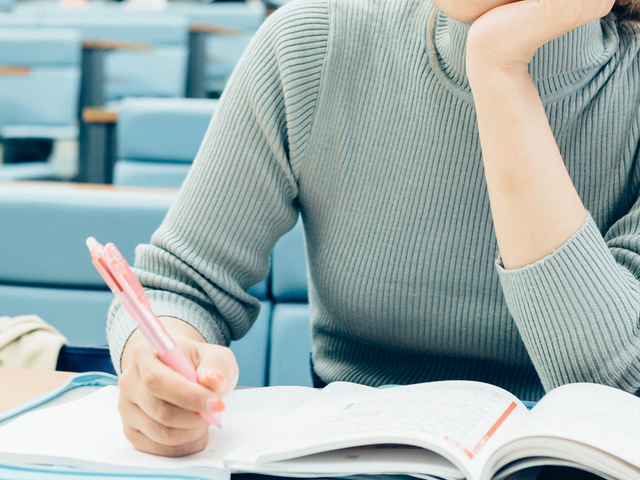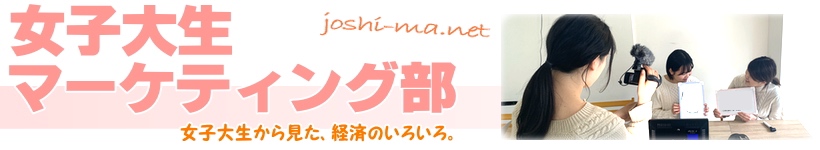こんにちは。女子大生マーケティング部2年の加古です。
私は小学生時代、ランドセルは定番の赤色では物足りず、ピンクローズのランドセルを使っていました。
MayLight社の「ランドセルの通知表」チームが、2019年3月〜5月にランドセルを購入した300名に対して行なった、ランドセルに関するアンケート調査の結果を発表しています。
▼購入したランドセルの色は?(女の子対象)
・赤 29.0%
・ピンク 24.7%
・紫(ラベンダー) 16.1%
・水色 10.8%
・キャメル 8.6%
・ブラウン 6.5%
・その他の色 4.3%
従来の定番だった赤色に並んで、ピンク色を選ぶ人も多いようです。現在はラベンダーや水色など多種多様なランドセルの色があって羨ましいです。

ランドセルと聞くと、小学生の頃を思い出しますね。小学生時代には習い事をしていた人も多いのではないでしょうか。私は最近、ピアノの魅力に気づき始め、ピアノを弾ける人に憧れを感じています。子供の頃は何も感じていなかったのに大人になってから心境が変わるケースも多いもの。
周囲の女子大生に、小学生の時にしていた習い事で現在も役に立ってることがないかどうか、聞いてみました。
●女子大生たちの声
▼小学生の時にしていた習い事で、現在も役に立ってることはありますか?
・水泳。基本的な泳ぎ方が身についた。プールや海に行っても怖くない。
・水泳。万が一の時を考えると安心。体の使い方を覚えられたし、体力もついた。
・ボーイスカウト。女子より男子の方が多かったためボーイスカウトに入ったが、性別や年齢関係なく仲良くなる能力がついた。キャンプなど自然の中で過ごすことが多かったため、雨が降っても全然平気だし、虫も大丈夫。規律訓練で回れ右など基本的な立ち振る舞いを教えてもらったので、その後の様々な式典で褒められた。ロープワークではロープの結び方を覚え、いざという時に人命救助ができるように。地図だけ渡されて東京を歩く訓練で、今でも地図アプリが無くても目的地にたどり着けるようになった。毎月の山登りや富士登山で、精神面がとても強くなった。自分の弱い心に勝つ意識を持つようになった。
・チアリーディング。体の柔軟さは、他のスポーツをする上でも役に立ったし、ストレッチをする習慣が身についたことで、運動能力賞も毎年もらうことができた。元々は笑うのが得意ではなかったが、練習していく中で、綺麗に笑えるようになり、営業のアルバイトなど人前に立つ時に役立った。チームで演技をするため、回りを見て動けるようになった。
・テニス。今のバイトがいくら立ち仕事でも何もきつくないし、他の女子よりは力仕事もできるなと感じる。
・少林寺拳法。危機意識の取り入れ方が変わった。少林寺拳法で一番大切なことは、技を身につけてるからと言って驕らずに、絶対に逃げること。何も守りを知らない状態で逃げろって教え込まれるのと、色々技を知った上でそれをその場でこなせるのは至難の業ってわかった上で逃げろって教えて込まれるのはわけが違う。急所を知っているので、何かあった時の判断力は磨かれた。
・ピアノ。リズム感や音感を鍛えられた。ダンスしたり歌ったり意外と応用できる場面が多い。
・ピアノ。楽譜が読めたから音楽の授業は楽勝だったし、ふと気が向いた時に軽く楽譜を読んで弾けるようになった。
・書道。スマホやパソコンが主流になっても、手書き文字が綺麗だと重宝される。自分で文字の書体を工夫することができ、ポスターなどを書く際に苦労しない。
・そろばん。頭の回転の速さが鍛えられた。暗算も早く、暗記力も身についた
・学習塾。どんな感じで勉強を進めたらいいのか、勉強のやり方を知れたから。
・理系の塾。ほぼ毎回実験があり、文系に進んでいたが22歳にして理系の資格取りたくなって、その塾で散々やった実験の経験が今とても役に立ってる。
・英会話。基本的な英語が身につき、同い年だけじゃなくて様々な年齢の友達ができた。
・生け花。和室での所作、礼儀作法を学ぶことができ、とても役に立っている。
・絵画教室。人に何かを説明するときに絵を使うことができるようになった。色の配色がわかる。絵を描くときに意識する空間感覚がわかることで、文化祭でも役立った。
・東京ガスが開催していた料理教室。料理を苦手意識を持たずにできるようになった。
・合唱。合唱曲をたくさん知ることができ、協調性を持てたり様々な音の聞き分けができたりするようになった。
スポーツ系で特に多かった回答は水泳。一方、文化系で多かったのはピアノでした。その時には何も考えずにがむしゃらにやっていたり、それほど好きではなかったりしても、大人になってみるとやっていて良かったと感じる方はすごく多いようです。
小学校の時の習い事はなかなかモチベーションが上がらないもの。でも、大学生ぐらいの分別のある世代に「どういうことに役立っているか」という情報がもっともっと発信されるならば、小さなお子さんはモチベーションを上げるきっかけになりそうです。